忙しいと、落ち着いて食事を準備する時間が取れません。外食が増えることで、健康やコストに影響が出やすくなるのも問題です。この記事では、外食のメリット・デメリットと、健康的かつ経済的に続ける工夫を紹介します。
記事を読めば、忙しい社会人でも、無理なく栄養バランスを整えながら外食を続ける方法が見つかります。健康的に外食を続けるには、栄養バランスと適量を意識することが大切です。小さな工夫で健康と効率の両方を意識して続けていきましょう。
» 理想的な食生活とは?健康的な食習慣を身に付ける方法を解説
毎日外食するメリット

外食中心の生活にも、以下のメリットがあります。
- 時間が節約できる
- 多様な食事を楽しめる
- 家事の負担が軽減できる
時間が節約できる
時間の節約は、毎日外食をする大きなメリットの一つです。忙しい一人暮らしの社会人にとって、限られた時間を有効に使える点は魅力です。外食を利用すれば、以下の時間を節約できます。
- 食事の準備の時間
- 食材の買い出しの時間
- 後片付けの時間
- 献立を考える時間
外食であれば移動中や仕事の合間にも食事が取れ、待ち時間を使って別の作業を進めることも可能です。食事に関する家事のストレスが減ることで、精神的な負担も軽くなります。食事の時間を柔軟に調整しやすく、忙しいスケジュールにも対応しやすくなります。外食を取り入れて、限られた時間を有効に使いましょう。
» ご飯を作りたくないときの対処法や便利な買い置き食品などを紹介
多様な食事を楽しめる

多様な食事を楽しめるのは、毎日外食する大きな魅力の一つです。和食や洋食、中華など、さまざまな料理を日替わりで味わえるため、食事の時間が楽しみになります。季節の旬の食材を使った料理や地域の特産品、本格的な味わいの名物料理にも出会えます。店舗ごとの個性的な雰囲気を楽しめるのも、外食ならではの魅力です。
気分に合わせて選べるので、食事が単調にならず、新たな料理や食材に触れる機会も広がります。多彩な食体験が、日々の生活に彩りを加えてくれます。
家事の負担が軽減できる
毎日外食することは、家事の負担を減らす一つの方法です。調理や食器洗いの手間がなくなり、買い物や食材管理、冷蔵庫の整理も不要になります。キッチンの掃除やゴミ出しの頻度も減り、キッチン用品の管理も簡素化されます。
家事から解放されることで、仕事や趣味に使える時間が増え、忙しい社会人にとって大きなメリットです。料理の失敗や食材の無駄を気にする必要がなくなるため、精神的な負担も軽くなり、生活にゆとりが生まれます。
毎日外食するデメリット
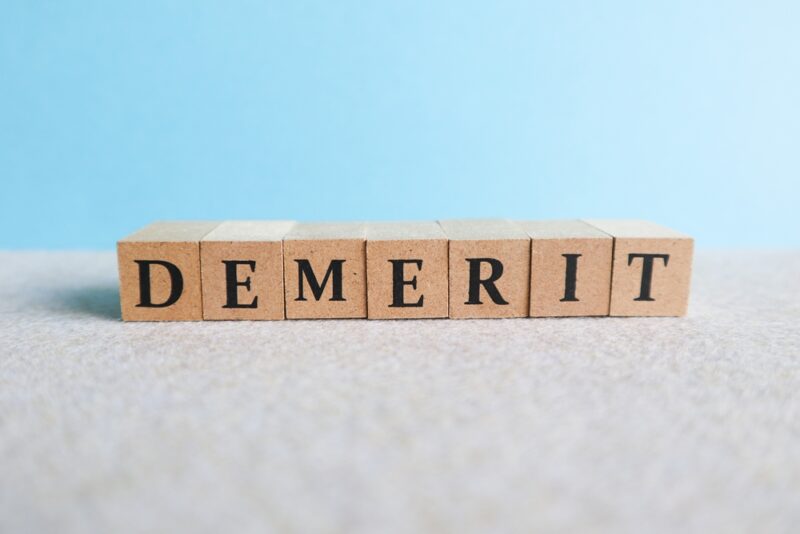
外食を続ける場合、以下のデメリットに注意が必要です。
- コストがかかる
- 栄養バランスが偏りやすい
- 健康リスクが増える
コストがかかる
毎日外食をすると、家計への負担が大きくなります。外食は自炊に比べて費用が高く、続けると月々の食費が大幅に増加します。外食には食材費だけでなく、人件費や店舗運営費も含まれており、高級店や夜の外食は高額になりがちです。飲み物やデザートの追加でさらに出費が増える場合もあります。
1食1,000円の外食を1日3回続ければ、月の食費は約9万円となり、自炊の3倍以上になる可能性もあります。長期的には貯金や他の生活費を圧迫する恐れがあるため、注意が必要です。
» 一人暮らしの食費の平均額や節約する方法を解説
栄養バランスが偏りやすい

毎日外食をすると、栄養バランスが偏りやすくなります。同じようなメニューの繰り返しや好みに偏った食事選択が原因です。野菜や食物繊維が不足しやすく、脂質や塩分の摂取量が多くなる傾向があります。タンパク質や炭水化物に偏りがちになり、ビタミンやミネラルが不足する恐れがあるため注意が必要です。
加工食品に頼ることで、季節の食材を取り入れる機会も少なくなります。栄養素の吸収が低下し、長期的な栄養不足につながる恐れがあります。バランスの取れた食事を意識することが大切です。
健康リスクが増える
毎日外食を続けると、健康に悪影響を及ぼす可能性が高まります。外食は便利ですが、続けすぎると健康リスクが高まるため注意が必要です。主な健康リスクには以下があります。
- 肥満
- 高血圧
- 生活習慣病
- 栄養不足
- 消化器系の問題
外食の頻度を減らすか、栄養に配慮したメニューを選ぶことが大切です。
毎日の外食を健康的にするためのポイント

健康的な外食を続けるために、以下の点を意識しましょう。
- バランスの取れたメニューを選ぶ
- サイドメニューで野菜を追加する
- 適量を心がける
- 低カロリー・低脂肪メニューを選ぶ
バランスの取れたメニューを選ぶ
毎日の外食でも健康を維持するには、バランスの取れたメニュー選びが重要です。主食・主菜・副菜のバランスを意識し、さまざまな食材が含まれるメニューを選びましょう。外食でも栄養バランスを意識するには、以下の工夫が効果的です。
- 和食や定食を選ぶ
- 彩り豊かな料理を選ぶ
- タンパク質・炭水化物・脂質のバランスを考える
- 季節の食材を取り入れる
栄養成分表示を確認し、バランスの良いものを選びましょう。加工度の高い食品や高カロリーメニューは控え、不足しがちな食物繊維やビタミン、ミネラルの摂取を意識することが大切です。一週間単位でメニュー全体のバランスを見直せば、長期的に健康的な食生活を維持しやすくなります。
忙しい社会人でも、ポイントを意識すれば、外食でも栄養バランスの取れた食事が可能です。
サイドメニューで野菜を追加する
サイドメニューで野菜を追加することは、毎日の外食を健康的にする効果的な方法です。忙しい一人暮らしの社会人でも手軽に実践できます。サラダや野菜の副菜、野菜スティック、カットフルーツを選ぶ方法があります。野菜ジュースやスムージー、野菜たっぷりのスープを追加するのも効果的です。
工夫次第で、ビタミンやミネラル、食物繊維を補え、栄養バランスも整いやすくなります。ただし、野菜を加えるだけでなく、バランスのとれた量を意識することが大切です。毎日の外食でも、選び方を工夫すれば健康的な食生活を維持できます。
» 推奨される1日の野菜摂取量と野菜を食べる量を増やすポイント
適量を心がける

適量を心がけることは、健康的な食生活を維持するうえで重要です。外食が中心でも、食べる量を意識すればカロリー摂取を抑えられ、体重管理にもつながります。小盛りや半量メニューを選ぶ方法があります。腹八分目で食事を終えたり、ゆっくりよく噛んで食べたりするのも効果的です。
工夫を取り入れることで、過食を防ぎながら適切な量の食事を続けられます。ただし、急に食事量を減らすと体に負担がかかるため、無理なく徐々に調整しましょう。自分の体調や活動量に合わせて、適切な食事量を見つけていくことが、健康と外食の楽しみを両立するポイントです。
低カロリー・低脂肪メニューを選ぶ
低カロリー・低脂肪のメニューを選ぶことは、健康的な外食習慣を維持するうえで重要です。カロリーを抑えることで、体重管理や生活習慣病の予防に役立ちます。カロリーや脂肪を抑えるには、以下のような選び方が効果的です。
- サラダやスープを主菜にする
- グリルやロースト調理の料理を選ぶ
- ドレッシングやソースは別添えにする
- 揚げ物や炒め物は避ける
- 低脂肪乳製品を使った料理を選ぶ
余分なカロリーや脂質を抑えながら、必要な栄養素を取り入れられます。蒸し料理や茹で料理を優先し、魚料理を積極的に選ぶのも効果的です。主食は全粒粉パンや玄米にすれば、食物繊維の摂取量を増やせます。カロリー表示のあるメニューを参考にすれば、より正確な管理ができます。
デザートを選ぶなら、フルーツを使ったものがおすすめです。低カロリー・低脂肪のメニュー選びや調理法の工夫を習慣にすれば、外食中心の生活でも健康的な食習慣を維持しやすくなります。
毎日外食でも栄養バランスを保つコツ

外食中心の生活でも、以下の方法を取り入れて栄養バランスを意識しましょう。
- サプリメントを活用する
- サラダバーを利用する
- 定食メニューを選ぶ
サプリメントを活用する
サプリメントを活用すれば、毎日外食をしていても不足しがちな栄養素を補えます。忙しい一人暮らしの社会人にとって、栄養バランスを整える手段として有効です。外食中心の生活で不足しやすい栄養素を補うために、以下のようにサプリメントを活用するのがおすすめです。
- マルチビタミン・ミネラルで幅広い栄養素を補う
- 食物繊維で腸内環境を整える
- オメガ3脂肪酸で不足しやすい脂質を補う
- プロバイオティクスで消化をサポートする
ただし、サプリメントに頼りすぎるのは避けましょう。食事を補う手段として取り入れ、栄養バランスの取れた食生活を心がけることが大切です。
サラダバーを利用する

サラダバーの活用は、毎日外食をする人にとって栄養バランスを保つうえで効果的な方法です。新鮮な野菜を豊富に摂取できるため、健康維持にも役立ちます。サラダバーでは、さまざまな野菜を組み合わせて選べます。季節の野菜を取り入れられる点も魅力です。自分で量を調整しやすく、低カロリーな食事にもつながります。
豆類やナッツ類が用意されている店舗も多く、タンパク質の補給が可能です。ドレッシングを減らすと、カロリーを抑えられます。食物繊維が多く含まれ、腸内環境の改善にもつながる食材です。鶏肉や卵などのタンパク質源を一緒に取り入れることで、栄養バランスの取れた食事になります。
サラダバーを上手に活用すれば、外食中心でも健康的な食生活を保ちやすくなります。
定食メニューを選ぶ
外食が多い人にとって、定食は手軽に栄養バランスを整えられる選択肢です。主菜や副菜、ご飯、汁物がセットになっているため、手軽にバランスの取れた食事が摂れます。特に和食中心の定食は健康的な選択肢としておすすめです。魚料理を含む定食は、良質なタンパク質や脂質を摂取できるメニューです。
野菜の種類が多いメニューを選ぶと、不足しがちな栄養素も補いやすくなります。定食には、栄養面以外にも以下のメリットがあります。
- 手頃な価格で楽しめる
- 季節の食材を取り入れられる
- 食べ過ぎを防げる適量に調整されている
- 作りたての料理を味わえる
味噌汁や茶碗蒸しなどの汁物も栄養価が高いため、一緒に注文するのがおすすめです。定食を取り入れることで、忙しい日々のなかでも健康的な食生活を維持しやすくなります。
毎日外食でも節約する方法

外食が続く場合でも、以下の方法を取り入れることで無理なく節約できます。
- クーポンやポイントを活用する
- お得なランチメニューを選ぶ
- テイクアウトを利用する
クーポンやポイントを活用する
クーポンやポイントを活用すれば、毎日の外食費を効率よく節約できるのでおすすめです。多くの飲食店が公式アプリを提供しており、ダウンロードするだけでクーポンを入手できる場合もあります。ポイントを貯めて、次回の会計での割引に活用しましょう。
食べログやぐるなびなどの予約サイトを利用すれば、割引やポイント付与が受けられる場合があります。還元率の高いクレジットカードを選ぶのも効果的です。SNSで最新情報をチェックしたり、メルマガ登録で限定クーポンを受け取ったりする方法もあります。
誕生日月の特典や学生・シニア向けの割引、グループ割引、期間限定キャンペーンなども活用しましょう。組み合わせて活用すれば、外食のコストをより効果的に抑えられます。
お得なランチメニューを選ぶ

お得なランチメニューを選ぶことは、毎日外食をする人にとって有効な節約方法です。ランチタイムは多くの飲食店が割安な価格設定をしており、上手に活用すれば食費を抑えられます。お得にランチを楽しむために、以下の方法を取り入れるのがおすすめです。
- 平日限定のランチセットを選ぶ
- 早割や時間帯限定のメニューを利用する
- 日替わりランチで変化を楽しむ
- ドリンクバー付きのセットを選ぶ
- 大盛りや増量オプションで満足感を高める
チェーン店は価格競争が激しいため、内容や価格を比較してお得な店舗を選ぶのも効果的です。ビュッフェ形式のランチでは、さまざまな料理を一度に楽しめますが、食べ過ぎには注意しましょう。クーポンアプリや店舗アプリのランチ特典を活用すれば、よりお得に食事ができます。
店舗のSNSで発信される限定サービスや割引情報をチェックするのも有効です。地域のランチマップやグルメサイトを活用すれば、新しい店舗やお得な限定メニューを見つけやすくなります。毎日の外食でもコストを抑えつつ、おいしく満足のいく食事を楽しみましょう。
テイクアウトを利用する
テイクアウトを利用することは、毎日外食をする人にとって大きなメリットがあります。外食のコストを抑えながら、時間の節約と食事の多様性を両立できるため、効率的な選択肢です。テイクアウトなら店内飲食より安く済む場合が多く、外食の回数を減らさずに食費を抑えられます。
食事の時間を自由に調整できたり、自分の好きな場所で食べられたりする点も魅力です。組み合わせ次第で好みのメニューにでき、残った分も後で食べられるため無駄がありません。行列や混雑を避けられるため、忙しい社会人にとっては時間の節約にもつながります。衛生面を自分で管理できる安心感もあります。
デリバリーと併用すれば、利便性が高まり、家族や同僚とシェアしやすくなるのもメリットです。テイクアウトを上手に活用すれば、毎日の外食生活を経済的かつ柔軟に楽しめます。
まとめ

毎日外食をする生活には、時間の節約や食の楽しみなどのメリットがある一方で、コストや栄養バランスの面で課題もあります。しかし、メニューの選び方や食べ方を工夫すれば、健康面と経済面の両方に配慮した外食が可能です。定食を選んだり、サラダバーを利用したり、サプリメントを併用したりする工夫が有効です。
クーポンを使ったり、テイクアウトを取り入れたりすれば、外食中心の生活でも無理なく健やかな食習慣を続けられます。
