健康を意識した食生活を送りたいと考えても、毎日の食事に気を配るのは大変です。全粒粉を取り入れた食事にすると、不足しがちな栄養の摂取が可能です。この記事では、全粒粉の特徴や栄養価、メリット、デメリット、選び方を解説します。
記事を読めば、忙しい日々を送る中でも、効率的に全粒粉の栄養を摂取できる方法がわかります。全粒粉は小麦粉と違って食物繊維が豊富です。血糖値の急上昇を抑える効果も期待できるため、健康に気を使っている方にも全粒粉は適しています。
» 体に良い食べ物の種類と効果|健康維持のポイント
全粒粉とは小麦を外皮や胚芽ごと挽いた粉のこと

全粒粉は小麦の外皮(ふすま)や胚芽、胚乳のすべてを含む栄養価の高い粉です。全粒粉に関する以下の3点を解説します。
- 全粒粉の特徴
- 全粒粉の製造方法
- 全粒粉と小麦粉の違い
全粒粉の特徴
全粒粉の特徴は風味が強く、つぶつぶの食感です。全粒粉の定義は国によって異なりますが、小麦粒の全成分を100%含むものです。小麦粉と異なり、全粒粉の見た目は茶褐色をしています。
全粒粉は以下の栄養素がバランスよく含まれています。
- 食物繊維
- ビタミンB群
- ビタミンE
- 各種ミネラル
GI値(血糖値の上昇指数)が低いため、血糖値の急上昇を抑えたい方に全粒粉はおすすめです。全粒粉はグルテンの形成力が小麦粉より弱いため、全粒粉でパンやお菓子を作る場合は固めの食感になります。水分吸収率が高いため、全粒粉を使用する場合は生地の水分量を多めにしましょう。
全粒粉の製造方法

全粒粉は小麦の粒を丸ごと粉砕して作られます。全粒粉の製造方法は、石臼製法と専用のローラーミルを使う方法があります。伝統的な石臼製法では、小麦を低速で丁寧に挽くのが特徴です。石臼製法で小麦を粉砕すると、熱の発生を抑えながら栄養素を守れます。専用のローラーミルは効率よく全粒粉を製造可能です。
小麦の粉砕の前に選別し、洗浄や調湿を行います。小麦の挽き方は「一段挽き」と「分離挽き後の再混合」があります。一段挽きは、小麦粒を一度に粉砕する方法です。分離挽きでは小麦の胚乳や胚芽、外皮を一度分離してから再び混合します。全粒粉の製造過程では温度管理が重要です。
製造中に高温になると全粒粉に含まれる貴重な栄養素が損なわれます。全粒粉の製造後は酸化を防ぐために、使用後はすぐに密封して保存されます。
全粒粉と小麦粉の違い
全粒粉と小麦粉の違いを以下にまとめました。
| 項目 | 全粒粉 | 小麦粉 |
| 粉の特徴 | 小麦の外皮・胚芽・胚乳を丸ごと挽いている | 胚乳部分だけを使って作られる |
| 色 | 茶褐色 | 白色 |
| 風味 | 香ばしい | マイルド |
| 栄養価 | 高い | 低い |
| 膨らみ | 小さい | 大きい |
全粒粉は酸化しやすいため、小麦粉より保存期間が短くなります。全粒粉を使ったパンやお菓子は小麦粉のものと比べて膨らみにくく、食感が重くなります。
全粒粉に含まれる栄養素

小麦のすべてを使用しているため、小麦粉よりも全粒粉は栄養価が高くなっています。全粒粉に含まれる栄養素は、以下のとおりです。
- 食物繊維
- ビタミンやミネラル
- 抗酸化物質
食物繊維
全粒粉は小麦粉に比べて、約3倍もの食物繊維を含んでいます。全粒粉に含まれる食物繊維は、水溶性と不溶性がバランスよく含まれています。水溶性食物繊維はコレステロール値を下げる効果があり、不溶性食物繊維は腸内環境を整え、便秘予防に有用です。
水溶性と不溶性の食物繊維は満腹感を持続させるため、食べ過ぎ防止にも役立ちます。全粒粉を100g摂取すれば、成人の1日の推奨摂取量(20〜25g)の約半分を摂取可能です。食物繊維は消化吸収を緩やかにする働きもあるため、血糖値の急上昇を抑制する効果も期待できます。
食物繊維はプレバイオティクスとして腸内細菌のエサになり、腸内環境を健康に保つ役割も果たします。朝食に全粒粉パンやシリアルを選べば、手軽に食物繊維の摂取量を増やすことが可能です。
ビタミンやミネラル

全粒粉は小麦粉と比べて、以下の栄養素が豊富に含まれています。
- ビタミンB群(B1・B2・B3・B6)
- ビタミンE
- 葉酸(ビタミンB9)
- 鉄分
- マグネシウム
- 亜鉛
- セレン
- カリウム
- マンガン
- リン
ビタミンB群はエネルギー代謝や神経機能の維持に役立ちます。ビタミンEには抗酸化作用があり、細胞を酸化ダメージから守ります。葉酸は細胞分裂や赤血球形成に必要な栄養素です。全粒粉には鉄分が小麦粉の約3倍含まれ、貧血予防に効果的です。マグネシウムは筋肉機能や心臓の健康維持に役立ちます。
亜鉛は免疫機能や細胞の修復、タンパク質合成のために重要な栄養素です。全粒粉に含まれるセレンには抗酸化作用があり、免疫力を高めるのに効果的です。カリウムは血圧調整や筋肉機能の維持に役立ちます。マンガンは骨形成や代謝機能に関わります。リンも骨や歯の形成、細胞機能に必要な栄養素です。
全粒粉で栄養素をバランスよく摂取すると、忙しい毎日でも健康的な体を維持できます。
抗酸化物質
全粒粉は体を守る抗酸化物質が豊富です。全粒粉に含まれるポリフェノールやフラボノイドなどのフェノール化合物は、細胞の酸化ダメージを防ぐ効果があります。全粒粉は老化防止や生活習慣病の予防に効果的です。小麦粉では、約60%の抗酸化物質が失われています。
全粒粉は加熱調理後も栄養成分が残存します。全粒粉パンや全粒粉パスタなどを取り入れると、手間をかけずに抗酸化物質を摂取可能です。全粒粉製品を日常的に取り入れると、免疫機能の向上につながります。
全粒粉の3つのメリット

全粒粉は通常の小麦粉に比べて栄養価が高く、栄養バランスを整えやすいのが魅力です。全粒粉のメリットは以下のとおりです。
- 栄養価が高い
- 血糖値が急上昇しにくい
- 香ばしい風味が楽しめる
栄養価が高い
全粒粉は日々の健康維持に欠かせない栄養素が豊富です。全粒粉には体内では合成できない必須脂肪酸の一種、α-リノレン酸が含まれています。α-リノレン酸は血管拡張作用があるため、高血圧予防に効果的です。全粒粉は小麦粉より良質なタンパク質が豊富です。
全粒粉を使った食品を選べば、1日の推奨摂取量の栄養素を効率的に摂取できます。全粒粉の栄養価の高さは単に栄養素の含有量だけではありません。さまざまな栄養素がバランスよく含まれているため、全粒粉は相乗効果も期待できます。全粒粉を日常的に取り入れると、健康的な食生活の基盤を作れます。
» 栄養バランスの基礎的知識とおすすめメニュー
» 理想的な食生活とは?健康的な食習慣を身に付ける方法を解説
血糖値が急上昇しにくい

全粒粉は小麦粉と比べて低GI値なため、ダイエットにおすすめです。全粒粉に豊富に含まれる食物繊維が、糖の吸収速度を緩やかにするためです。消化に時間がかかるため、全粒粉は体内でのエネルギー放出がゆっくり行われ、血糖値が急激に上がりにくくなります。
血糖値の上昇が緩やかになると食後の眠気を防止でき、仕事の効率を維持できます。全粒粉による血糖値の安定効果は、以下のとおりです。
- インスリンの急激な分泌を抑える
- 血糖値の乱高下を防ぐ
- 食後の満腹感が長続きする
- 間食や過食を防止できる
- エネルギーレベルが安定する
普段の食事で小麦粉を全粒粉に置き換えるだけでも、血糖値コントロールに効果的です。全粒粉の摂取は、2型糖尿病リスクの低減にも貢献します。食物繊維と他の栄養素の相乗効果によって代謝も改善されるため、全粒粉は健康的な体重維持にも役立ちます。
香ばしい風味が楽しめる
全粒粉はナッツのような深い香ばしさを持っており、複雑で豊かな味わいを楽しめます。小麦の外皮部分に含まれる成分が焼成時に独特の風味を生み出すためです。全粒粉を使ったクッキーやパン、ピザなどがおすすめです。
全粒粉を軽くフライパンでローストしてから使うと、さらに香ばしさが引き立ちます。風味が強いと感じる場合は、全粒粉と小麦粉を混ぜて好みの香ばしさに調整しましょう。最初は全粒粉の割合を3割程度から始めて、徐々に比率を上げていくのもおすすめです。
全粒粉の香ばしさを生かしつつ他の素材とのバランスを考えると、味わいに深みのある料理が完成します。
全粒粉の3つのデメリット
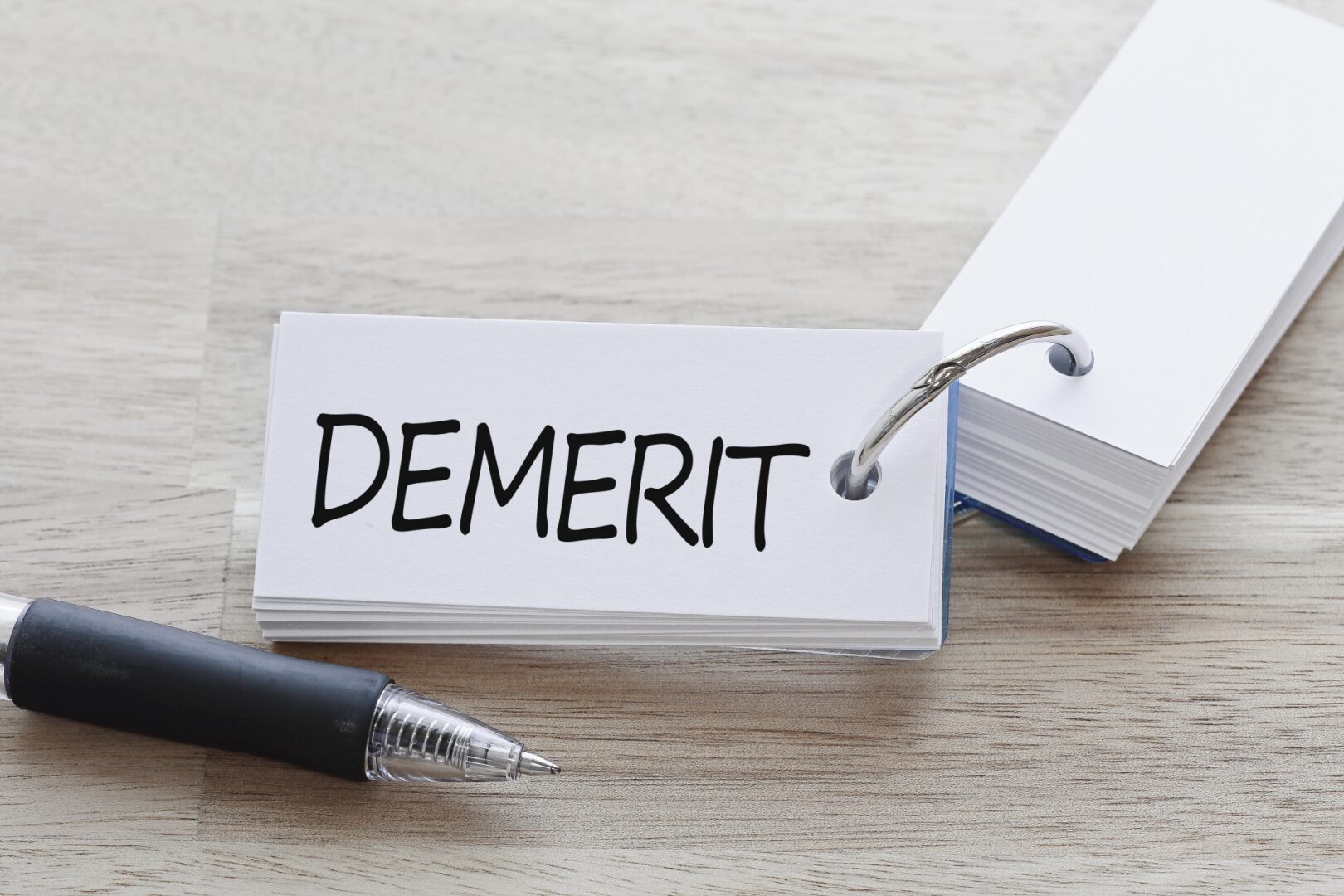
全粒粉には健康効果がある一方で、以下のデメリットも存在します。
- 消化に時間がかかる場合がある
- 酸化しやすい
- フィチン酸が栄養吸収を妨げる場合がある
消化に時間がかかる場合がある
全粒粉に含まれる食物繊維により胃での滞留時間が長くなるため、消化に時間がかかります。全粒粉を摂取すると、胃もたれや膨満感、消化不良を起こす場合もあります。急に食生活を変えると体に負担がかかるため、徐々に体を慣らしていくのが効果的です。
全粒粉に慣れていない方は、少量からはじめて徐々に摂取量を増やすことをおすすめします。消化器系に持病がある場合は、事前に医師に相談してから全粒粉を取り入れましょう。
酸化しやすい

全粒粉の胚芽と外皮には油分が多く含まれているため、小麦粉よりも酸化しやすくなります。開封後の全粒粉は1〜2か月程度で酸化が進行するため、早めに消費しましょう。全粒粉の室温での長期保存は、酸化のスピードを早めます。
酸化した全粒粉は独特の苦味や臭いが発生するため、料理の風味や品質を著しく低下させる場合があります。全粒粉の栄養素を最大限に生かすためにも、適切な保存方法を心がけましょう。
フィチン酸が栄養吸収を妨げる場合がある
フィチン酸は全粒粉に含まれる天然の物質で、体内での栄養吸収を妨げる場合があります。ベジタリアンや普段からミネラル摂取が少ない方は、全粒粉を摂取する際に注意しましょう。発酵させた全粒粉のパンを選んだり、全粒粉を使う前に水に浸したりすると、フィチン酸の影響を減らせます。
バランスよく食事をしていれば、全粒粉の摂取量について過度に心配する必要はありません。フィチン酸には抗酸化作用や発がん抑制効果などのメリットもあるため、適度な全粒粉の摂取は健康に役立ちます。
全粒粉の選び方と保存方法

全粒粉は適切な選び方と保存方法で、栄養価と風味を最大限に生かせます。質の良い全粒粉の選び方と、正しい保存方法を解説します。
質の良い全粒粉の選び方
質の良い全粒粉を見極めるには、製造日が新しい製品を選ぶのが大切です。全粒粉は胚芽を含むため酸化しやすく、時間が経つほど栄養価や風味が落ちます。選ぶときは「100%全粒粉」や「有機認証」の表示がある製品もポイントです。濃い茶褐色で添加物が少ない製品に注目すると、良質な全粒粉を見分けられます。
遮光性パッケージが使用されている全粒粉製品を選ぶのもおすすめです。国産小麦を使用しているかも重要です。保存方法は冷蔵、または冷凍保存されている全粒粉を優先して選びましょう。全粒粉は料理の用途に合わせて粒度(細挽き・中挽き・粗挽きなど)を選ぶのも大切です。
パンには中〜粗挽き、お菓子やケーキには細挽きの全粒粉が適しています。質の良い全粒粉を選ぶと、栄養価の高さと独特の風味を最大限に生かした料理を楽しめます。
正しい全粒粉の保存方法
全粒粉は密閉容器に保存して湿気を避けましょう。全粒粉の保管場所は冷蔵、または冷凍が最適です。冷蔵では1〜3か月以内、冷凍は6か月以内の保存が目安です。全粒粉は使用時に必要な分だけ取り出し、残りはすぐに密閉して元の場所に戻します。
他の食品の臭いを吸収しやすいため、強い香りのする食品と全粒粉は離して保存しましょう。保存中に異臭や虫の発生が見られた場合は全粒粉の品質が劣化している可能性があるため、使用を避けてください。
全粒粉に関するよくある質問

全粒粉に関するよくある質問は、以下のとおりです。
- 全粒粉はグルテンフリー?
- 全粒粉のアレルギーリスクは?
- 全粒粉の摂取量の目安は?
全粒粉はグルテンフリー?
全粒粉は小麦タンパク質であるグルテンを含んでいるため、グルテンフリーではありません。セリアック病(自己免疫疾患)や非セリアック性グルテン過敏症の方は、全粒粉を含む食品の摂取を避けましょう。
グルテンフリーの代替品には、以下の製品がおすすめです。
- アーモンド粉
- ココナッツ粉
- 玄米粉
- そば粉
- あわ粉
製造工程で交差汚染する可能性もあるため注意が必要です。グルテンアレルギーの方は、パッケージに「グルテンフリー」と明記されている製品を選びましょう。
全粒粉のアレルギーリスクは?

全粒粉は小麦から作られるため、小麦アレルギーの方は注意が必要です。小麦アレルギーの症状は人によって異なりますが、以下の症状が現れる場合があります。
- 蕁麻疹
- 呼吸困難
- 消化器症状
グルテン不耐症(セリアック病)の方も全粒粉の摂取を避けましょう。全粒粉には小麦粉と同じ量のグルテンが含まれているためです。全粒粉製品を購入する際はパッケージのラベルを確認し、他のアレルゲンとの交差汚染にも注意しましょう。
全粒粉の摂取量の目安は?
全粒粉の摂取量の目安は1日90gです。1日に1〜2枚の全粒粉パンを食べると、効率的に食物繊維を摂取できます。無理なく全粒粉を摂取できるように、1日1〜2回の食事に分けて取り入れるのがおすすめです。ただし、最適な全粒粉の摂取量は、個人の健康状態や消化機能によって異なります。
体調を見ながら自分に合った全粒粉の摂取量を見つけていくのが大切です。お腹の調子が悪くなったら、全粒粉の量を減らすなど、柔軟に調整しましょう。
まとめ

全粒粉とは、小麦の外皮や胚芽も含めて丸ごと挽いた栄養価の高い食材です。全粒粉には食物繊維やビタミン、ミネラル、抗酸化物質を含み、血糖値の急上昇を抑える効果が期待できます。消化に時間がかかり、酸化しやすいため、全粒粉を摂取する際は注意しましょう。
全粒粉を取り入れる際は質の良い全粒粉を選び、冷蔵庫や冷凍庫での適切な保存が重要です。全粒粉はグルテンを含むため、小麦アレルギーのある方は注意しましょう。手軽に栄養価の高い食事を摂りたい場合は、全粒粉製品を取り入れると、健康的な食生活を維持できます。
